精液検査はなぜ病院では良くならないのか?
男性不妊の検査としてよく行われる「精液検査」
数値を見て、「良くない」と言われた経験のある方も多いのではないでしょうか。
そして、その後「数ヶ月たっても変わらない」「病院で何もできないと言われた」という声もよく耳にします。
なぜ、病院で精液検査の数値が良くならないのでしょうか?
病院の役割と限界
病院では主に、ホルモンの数値や精子の有無、運動率などの「結果」をチェックします。
しかし、「なぜ今の状態になっているのか?」という原因の掘り下げや、日常の体づくりまではアプローチしないことが多いです。
また、検査後に「自然妊娠は難しいですね」「体外受精を考えましょう」と言われ、
「じゃあ、自分で何をすればいいの?」と迷われる方も少なくありません。
精液は“体全体の状態”を映す鏡
精液の質は、単に「生殖器の働き」だけで決まるわけではありません。
以下のような体全体の要素が、大きく影響しています。
- 睡眠の質とホルモン分泌
- 食事のバランスとミネラルの吸収力
- 肝臓や腸の働き
- 自律神経のバランス
- 血流の状態や体の冷え
つまり、「精子の状態」=「今の自分の体の状態」なのです。
このような視点から見ると、精液の質を変えていくためには、
「数値だけを見る」のではなく、「体全体を整えていく」ことが欠かせないのです。
数値を“上げる”ではなく、“育てる”という発想
精子は“急成長”するものではありません。
約70〜90日かけて、少しずつ作られ、育ち、ようやく精液として排出されます。
つまり、「今日から〇〇を始めたから、来週には変わる」というものではないのです。
コツコツとした体づくりの積み重ねが、数ヶ月後の結果に表れるというイメージです。
病院での検査結果は、未来を決めるものではなく、“今の体の状態の通知表”。
だからこそ、焦らずに、自分の体と向き合っていくことが大切なのです。
東洋医学の視点から
東洋医学では、精子をつくる力は「腎」の働きと深く関わっているとされています。
「腎」は生命力の源とされ、年齢やストレス、過労、不摂生によって弱まりやすいと考えられています。
また、血流や内臓の働き、自律神経の乱れも「精のめぐり」に影響を与える要素です。
当院では、こうした全体のバランスを見ながら、体づくりをサポートしています。
最後に
精液検査の数値に落ち込むことがあっても、それは「まだやれることがある」という体からのメッセージでもあります。
病院の検査は大切な指標の一つですが、そこで終わりにせず、
「自分の体にできること」を見つけていくことが、新しい一歩になるはずです。
この記事に関する関連記事
- なぜ顕微授精はなかなかうまくいかないのか?
- 男性不妊症を最短で改善するためにすべきこと
- 肝臓の代謝機能と精子の健康の関係
- 精巣の神経と男性不妊|精子の健康を支える神経バランスとは?
- 男性不妊と過食|脳のメカニズムから考える過食とその対策
- 男性不妊症とセロトニン|精子の健康を支える「幸せホルモン」
- 男性不妊症とざくろ酢|精子の健康をサポートする抗酸化の力
- 男性不妊とトランス脂肪酸|精子の質を守るためにできること
- 男性不妊と血糖値管理|バルサミコ酢の健康効果とは?
- 男性不妊症のブログ一覧
- 無精子症でも精子が見つかる可能性は?
- 睡眠の質が精子の質を左右する?|男性不妊と睡眠アプリの活用
- 東洋医学で考える男性不妊|「気虚タイプ」の特徴と改善策
- 男性不妊と東洋医学の視点 〜虚証と実証から考える〜
- 外食でも健康的に!小麦・トランス脂肪酸・食品添加物を避ける食べ方ガイド
- ターメリックと男性不妊症—スパイスの力で精子の健康をサポート
- 男性不妊とデトックスの関係:体内環境を整えるためのヒント
- 男性不妊症と副腎ホルモンの関係について
- 男性不妊症とミトコンドリア—精子の健康を守る9つのアプローチ
- 電磁波と男性不妊症—アーシングで精子を守る新習慣
- 腸活で自律神経を整え、男性不妊症を改善する—精子の健康をサポートする新習慣
- 男性不妊症と胆汁—精子の健康を支える消化液の力
- 男性不妊症とインターミッテント・ファスティング(断続的断食)—精子の健康を守る新しい食事法
- 男性不妊症と骨盤底筋トレーニング—精子の健康と男性力を高める秘訣
- 果糖と男性不妊症の関係—加工食品が精子の健康に与える影響
- 男性不妊症と抗老化遺伝子—若返り効果で精子の健康をサポート
- クロレラとベントナイトクレイによるデトックス方法
- 男性不妊症とミトコンドリア—精子の健康を支えるエネルギーの鍵
- 子宮内膜とは
- 子宮内フローラ
- 排卵検査薬の使い方
- 男性不妊症とイカリソウエキス—活力を高め、精子の健康をサポートする自然の力
- 男性不妊症と腎の気—生命力を高めるための東洋医学的アプローチ
- 男性不妊症とパクチー デトックス効果で精子の健康をサポート
- 男性不妊症とケトフレックス—精子の健康を支える柔軟な食事法とは?
- 男性不妊症とピラティス—体幹を鍛え、ホルモンバランスを整えるエクササイズのすすめ
- 妊娠中に摂るべき控えるべきサプリメント
- 男性不妊症に「生姜オイル」で体質改善を目指そう
- 男性不妊症と糖質—腸内環境を整え、精子の質を高めるために知っておきたいこと
- 男性不妊症と腸カビ—腸内環境が精子の健康に与える影響とは?
- 男性不妊症とカンジダ菌—腸内環境が精子の健康に与える影響とは?
- 男性不妊症と食品添加物—精子の健康を守るために知っておきたいこと
- 男性不妊症と筋トレ—精子の質を高める効果とその理由
- 男性不妊症とお酒—飲むなら蒸留酒がオススメな理由
- 男性不妊症と睡眠—スタンフォード式睡眠法で生殖機能を改善する
- 男性不妊症と肝臓の健康—知られざる肝機能の重要性
- 男性不妊症とミネラル—亜鉛とセレンの重要な役割 + ミネラルデトックスの必要性
- 男性不妊症とPQQ—エネルギーと抗酸化力で精子を守る!
- 男性不妊症の原因:遺伝子と生活習慣の影響
- 男性不妊症とマグネシウムの関係:健康な精子を育む鍵
- 精子の質を向上させる!抗酸化食品とサプリメントの効果的な選び方
- 精子力を高める良質な脂質:MCTオイルとオメガ3脂肪酸の違いとは?
- MCTオイルで精子力アップ!妊活中の男性におすすめの健康効果
- リンゴ酢が精子力をサポート?妊活中の男性におすすめの健康効果
- 男性不妊と「大腰筋」~腰の冷えが精子力に与える影響~
- 腸と精子の質の関係:腸内フローラを整える1週間の食事プラン
- 腸から精子力をアップ!短鎖脂肪酸が精子の健康を守る理由
- 酸化ストレス対策で精子DNAを守る!抗酸化食品と習慣
- 糖化を防いで精子力を守る!体内の“焦げつき”が妊活に与える影響
- ポジティブな言葉が精子力を高める!アファメーションで心と体を整える
- デトックスで精子力アップ!ミトコンドリアと重金属対策
- 男性不妊症とミトコンドリア⑥—有害重金属
- 男性不妊症とミトコンドリア⑤—性ホルモン
- 男性不妊症とミトコンドリア④—甲状腺ホルモン
- 男性不妊症とミトコンドリア③—副腎ホルモン
- 男性不妊症とミトコンドリア②—肝臓デトックス
- 男性不妊症とミトコンドリア①—腸内環境
- ミトコンドリアと精子・卵子の関係
- 腸内環境を整えることが、男性の健康と妊活の一歩に!
- 男性不妊と日常の習慣―精子の健康を守る生活習慣とは?
- 男性不妊と冷え対策―血流を改善し、体を温める方法
- 男性不妊と食生活―精子の質を高める栄養素と食事法
- 男性不妊と運動習慣―おすすめのエクササイズとその効果
- 男性不妊とストレス―心の健康を整える方法とは?
- 睡眠が人体へ与える影響と「良質な睡眠」とは?
- 「ミネラル」の効果的な摂り方
- 「タンパク質」の効果的な摂り方とは?
- 男性不妊症と見た目年齢
- ケトジェニック食をしながら体重を増やすには
- リーキーガット症候群について
- 男性不妊改善に!けずり粉で始める手軽な栄養サポート
- エネルギーとホルモンを整える!ビタミンB群で妊娠力アップ
- 前立腺もホルモンも!妊活に効くパンプキンシードの6つの効果
- 男性も必見!ビタミンDが妊娠率を高める秘密とは?
- 精子の質を守るカギ!グルタチオンの驚きの効果とは?
- 妊活を始める前に知っておきたい!不妊症改善に役立つ検査の全貌
- 髪も体も元気に!ゼラチンで男性不妊と薄毛を同時にサポート
- あなたの体、大丈夫?男性の老化サインを見極める10の質問
- 女性の基礎体温の秘密:妊娠しやすい体づくりのヒント
- 精子と卵子に必要な亜鉛の力、今すぐ取り入れよう
- 未来を変えるのは今!男性妊活、まずは体を知ることから
- 姿勢改善で男性の妊娠力アップ!内臓から精子まで健康をサポートする秘訣
- 妊娠力をアップ!妊活に欠かせないビタミンの力とは?
- 妊娠力アップのカギ!良質な油で妊活をサポート
- 妊活栄養素③【鉄分】吸収率を上げて妊娠力アップ
- 妊活栄養素②【タンパク質】毎日のタンパク質で体を整えよう
- 妊活栄養素①【基礎編】生殖器への栄養が不足?妊活成功のための栄養管理
- 現代人が抱える栄養不足!サプリメントが必要な理由とは?
- 精子の見えないダメージ!DNA損傷が妊娠に与える影響とは?
- 卵子を守る!酸化ストレスが妊娠に与える影響とは?
- 「血糖値が精子に影響 男性不妊と炎症の知られざる関係」
- 卵子の質が妊娠成功のカギ:本当の妊活サポートとは
- 不妊率世界一の日本が抱える課題とその解決策
- 【男性不妊症】とセリアック病
- ダイエットで精子力を高める!脂肪酸を取り入れた食生活のすすめ
- 【男性不妊症】と「グリアジンタンパク」
- 男性不妊症と精子の細胞損傷
- 【消化機能】と男性不妊症
- 【ヴィーガン】と男性不妊症
- 【自律神経】と男性不妊症
- 【野菜のリスク】と男性不妊症
- 【睡眠の質】と男性不妊症
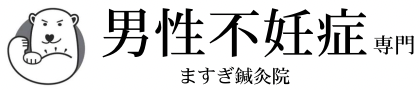





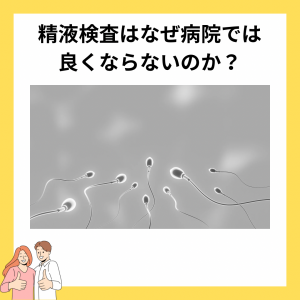
お電話ありがとうございます、
ますぎ鍼灸院でございます。